日本文化学科の授業紹介
科目 Close up
日本文化学科の授業をピックアップしてご紹介します。
科目 Close up日本文学概説

日本文学の作品を鑑賞・研究するための土台を作る
日本文学のさまざまな作品を読みながら、鑑賞・研究のために必要な概念や基礎的な知識を学びます。
書物の装訂や広まりを入り口に、漢字の伝来と仮名の成立、神話や物語に見られる貴種流離(きしゅりゅうり)の話型、無常観、史実と虚構の問題、後代の読者による受容、和歌の修辞技法などについて学び、各時代の表現や美意識、思想に迫ります。
科目 Close up日本語教育A
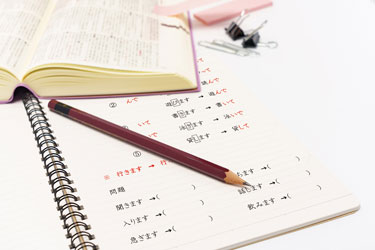
日本語を母語としない人に日本語を教える。その専門性と社会的意義を考える。
これからの日本には、外国からの移住者が増えていくでしょう。日本語を母語としない人たちが、地域で安全に、安心して暮らすためには、どのような日本語が必要で、どのような教育が求められるでしょうか。この授業では、日本語学習者や教育現場の多様性を尊重し、柔軟に考え、適切に対応できる力を身につけるための基礎的な姿勢を学びます。
科目 Close up日本史の研究(中世史特論)

中世後期の東国における戦乱が、政治や社会に及ぼした影響について学ぶ。
近年の研究の目覚ましい進展により、中世後期(室町~戦国期)の東国に関する歴史的事実が次々と明らかになっています。講義ではこのような研究成果を紹介するとともに、これまで一般的にはあまり顧みられることのなかった室町・戦国期の埼玉県域(武蔵国)の歴史について理解を深めていきます。
科目 Close up日本史の研究(近代史特論)
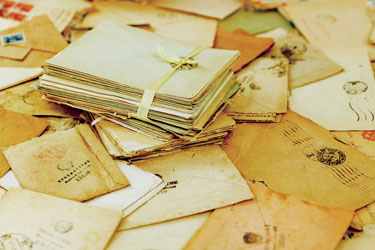
劇作家・三好十郎の人生から読み解く近代日本の戦争、そして平和
三好十郎は、激動の近現代日本を「火だるま」のように生きた一人の劇作家です。プロレタリア作家として出発した三好は、日本が軍国主義体制へと進む中で「転向」を経験し、戦時下においては戦争協力の一端を担うことになりました。そのような三好の歩みについて、残された演劇作品のみならず、同時代の社会状況や思想の変化に注目しながら検証します。
科目 Close up文学理論

物語を織りなす文学作品には規則や法則があるということを先人の研究から学ぶ
この授業では、文学作品を学術的に解釈していくために必要な文学の理論、つまりその作品の背後にある規則性や法則性といったものを、これまでの研究成果から学びます。高校までの正解を見つけるといった国語的なアプローチからではなく、物語の構造やスピード、語り手の位置など既存の理論を用いて、作品の本質に迫っていきます。
科目 Close up中国文学

高校までの「漢文」の学びを磨き上げ、中国古典の世界を自在に探求する。
この授業では六朝時代の志怪小説の代表作である『捜神記』の記事を素材として、漢文読解の基礎力を身につけつつ、中国の古典作品を扱うための基本的な技術の習得、比較文化の着想を学びます。志怪小説とは「怪」の簡潔な記録という意味になります。授業では本文の丁寧な読解から日本の妖怪談義へと全力で「脱線」します。
科目 Close up比較文化概論

近現代日本人の異文化体験とその近代的な受容の姿についての調査、分析と理解
開国後、多くの日本人が海外に渡り、渡った国や地域の文化や技術を学び、その後、必要に応じてそれらは日本国内に持ち込まれている。この授業では、その中でも日本の近代化と密接に結びついた日本人の海外での異文化体験について、彼らの当地での動静を伝える日記や新聞記事などから分析し、日本の近代化を追体験しながら学んでいきます。
科目 Close up教えるための古典

国語科教員になるために必要な古典文学とその指導法を学ぶ
将来、中学校・高等学校で指導するために必要な古典文学の指導法の基礎を2年かけてじっくり築きます。
古文と漢文の文法、作品読解・鑑賞方法、文学史、指導法について、それぞれを専門とする担当者から学び、古典の豊かな世界を楽しみ、指導するための素養と方法を身に付けます。


