NEWS
お知らせ
子ども教育学科
「不適切な保育」から子どもを守り、保育者自身をも守るために(子ども教育学科:田澤薫教授)
子ども教育学科の「保育・教職実践演習(幼)」
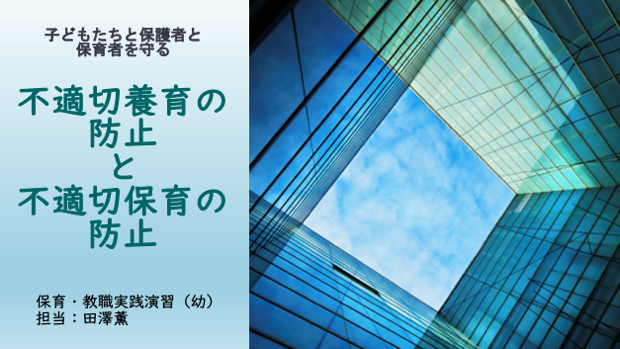
「不適切保育」の事件報道が相次いでいます。学生からも「将来 不適切保育をしてしまったら...」という不安をききます。どの保育者も、子どもが好きで保育職に就いたはずです。それでも人間は弱いもの、悪条件が重なれば私も...と当事者意識をもつ学生たち、誠実な心配だと思います。
卒業生を不適切保育から守りたい。そこで、子ども教育学科では、4年生の「保育・教職実践演習(幼)」で、今年は「不適切保育の防止」も取り上げることになりました。
子どもを人格として捉えることを、子ども教育学科では4年間かけて学んできました。子どもを「言うことをきかせる対象」ではなくて人格として捉えられるのは、保育者自身の人格に他なりません。そのことをまず認識する必要があります。4年間の学びで付いた力を振り返り新たな視点から認め直すことで、自らに備わった力に気付き、ハラスメントのパワー関係が生じないために社会でなされている工夫(厚生労働省や自治体が出している手引きやガイドライン、全国保育士会のセルフチェックリスト、第三者評価制度等、いろいろあります)についても理解を深めました。
提出されたリアクションペーパーの洞察は深く、やさしく温かく保育者らしい言葉選びでした。大学のポータルサイトUNIPAで個々に返信しながら、4年の歩みが思われました。
一人一人の保育者としての歩みが幸いでありますように。

卒業を控えた4年生たちが真剣に学んでいます。
科目について
「保育・教職実践演習(幼)」(15コマ)は保育士課程・幼稚園教職課程の最後の必修科目です。卒業を控え、資格・教職課程で力をつけてきた歩みを「教職履修カルテ」を通して振り返ると共に、すでに学んだあとに法令改正があった事項や新たに社会問題になっている事項について学修を補い、専門職としてのはたらきに備えます。子ども教育学科では、毎年、その年の4年生の4年間を振り返り、必要な15コマ分の教授内容を吟味して授業計画を調整しています。


